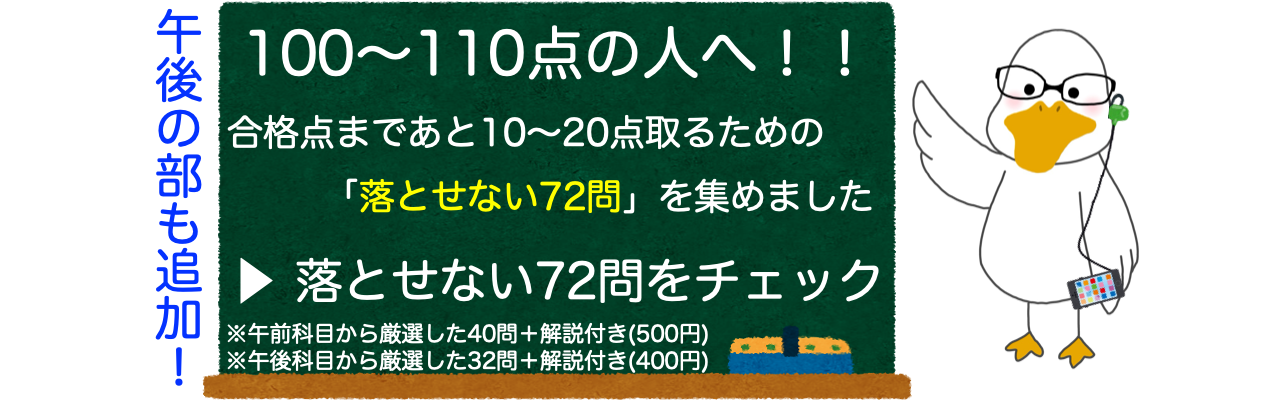⑴ 一次性ネフローゼ症候群では、LDLコレステロール値が〔 上昇 〕する。
ネフローゼにより、尿中にアルブミンが流出すると、低アルブミン血症が生じる。
減ったアルブミンを補うために、肝臓はアルブミン合成を増加し、どんどん供給する。
(結局、ネフローゼで流出するため低アルブミン血症のまま)
肝臓がアルブミンを合成するときに、”ついでに”コレステロール合成も増加するので
結果的に血中LDLコレステロール値は増加する。
⑵ 急性腎障害(AKI)では、血清クレアチニン値が〔 上昇 〕する。
急性腎障害(AKI)では、腎機能が低下するため、血清クレアチニン値が上昇する。
その結果、血清クレアチニン値や年齢・性別から算出するeGFRは低下する。
⑶ 微小変化型ネフローゼ症候群では、たんぱく質摂取量は〔 ほぼ制限しない(1.0~1.1 g/kg) 〕。
微小変化型ネフローゼ症候群ではほとんど食事制限をしない。
エネルギー35kcal/kg, たんぱく質 1.0~1.1 g/kg,
食塩0~7 g (幅が広すぎるので国試に出しづらい)
カリウム(mg/日)→血清カリウム値によって決める。
⑷ 急性糸球体腎炎の乏尿期では、食塩を〔 3g/日未満 〕とする。
急性糸球体腎炎の乏尿期には食塩制限を厳格(3g/日未満)に行う。
〇⑸ 腹膜透析では、食事のエネルギー量は、目標エネルギー量から、腹膜吸収ブドウ糖のエネルギー分を差し引いて求める。
正しい。エネルギー摂取量の計算などでも登場するので覚えておきたい。
腹膜透析の透析液は濃度の高いグルコース溶液を用いて、浸透圧の原理で体内から除水する。
文責:アヒル
😫 解説を読むのに疲れたら・・・
気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?
無料で試してみてね(期間中に解約で0円)
※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照
(PR)国試本番のためにマークシート専用の鉛筆は買った?