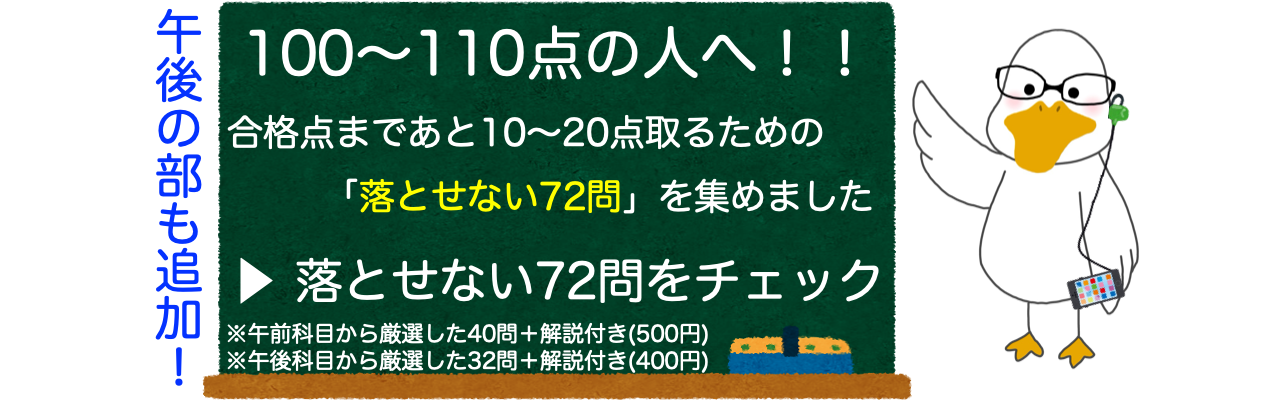⑴ 食行動異常は、認知症の〔 行動心理症状 〕である。
認知症には、中核症状と行動心理症状がある。
中核症状:記憶障害・見当識障害・遂行機能障害
行動心理症状:異食や過食などの食行動・不安・不眠・徘徊
などに分けられる。
⑵ 認知症のスクリーニングには、〔 MMSE 〕が用いられる。
38-135(2)に関連して、DESIGN-Rは「褥瘡の重症度」を判定するツールである。
https://nstudy.info/38-135/
よって、選択肢の認知症スクリーニングには用いない。
認知症のスクリーニングにはMMSEなどが用いられる。
MMSEについては39-94を参照のこと。
https://nstudy.info/39-94/
〇⑶ パーキンソン病では、嚥下障害がみられる。
正しい。
パーキンソン病では安静時振戦や姿勢不安定の他に嚥下障害、便秘・失禁が見られる。
⑷ パーキンソン病では、エネルギー目標量を安静時エネルギー消費量の〔 1.1〜1.3 倍 〕とする。
パーキンソン病では安静時振戦などによりエネルギー消費量が亢進しているが、2倍にするほどのものではない。
増やしたとしても、1.1〜1.3倍程度までである。
⑸ レボドパ(L-ドーパ)は、薬の効果を高めるために、〔 低たんぱく質食 〕と一緒に内服する。
薬と食事の相互作用の問題としてよく出題されるので覚えておきたい。
レボドパ(L-ドーパ)は、高たんぱく質と一緒に摂取すると
吸収が阻害され、結果的に薬の効果が弱まってしまう。
そのため服薬するときの食事のみ「低たんぱく質食」とし、その他の食事でたんぱく質をしっかりと摂る。
※レボドパはフェニルアラニンやチロシンから合成されるアミノ酸の一種であり、
レボドパの吸収はその他のアミノ酸と同じ経路・輸送担体で吸収されていく。
したがって、高たんぱく質食と同時に摂取すると、
たんぱく質由来のアミノ酸と競合(入口の取り合い)し、吸収率が低下する。
文責:アヒル
😫 解説を読むのに疲れたら・・・
気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?
無料で試してみてね(期間中に解約で0円)
※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照
(PR)国試本番のためにマークシート専用の鉛筆は買った?