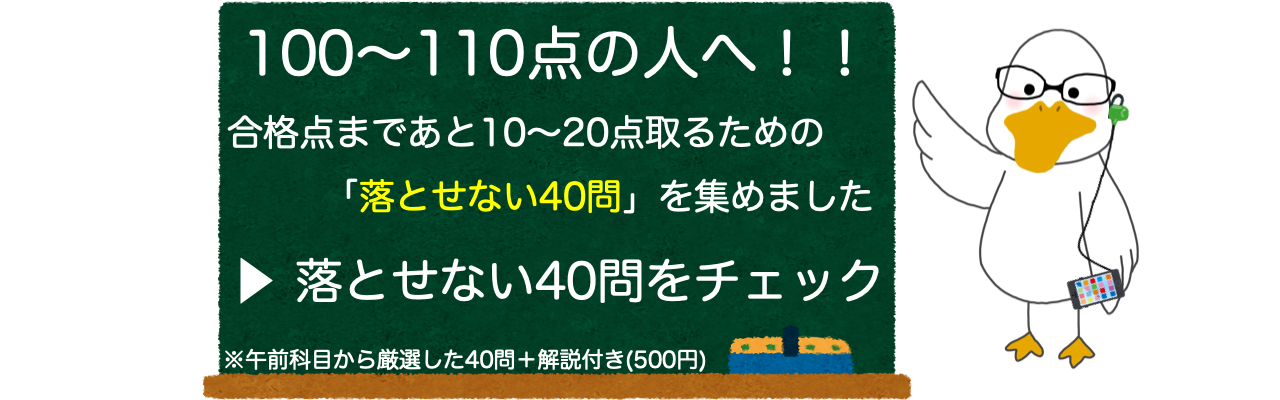経口血糖降下薬は頻出であるためしっかりとおさえておきたい。
〇⑴ α-グルコシダーゼ阻害薬は、二糖類の分解を抑制する。
α-グルコシダーゼという酵素は小腸の膜表面に存在する酵素で
マルターゼ(グルコースx2の二糖類)を分解する酵素である。
食事から摂取したでんぷんは唾液や膵液に含まれるアミラーゼによって分解され
その後、この酵素によって最終の分解が行われ速やかに吸収される。
α-グルコシダーゼ阻害薬は、この酵素を阻害するので
糖の吸収を一部阻害(糖の吸収を穏やかに)し、食後高血糖を回避することができる。
トクホの成分であるグァバ茶ポリフェノールは、この酵素を阻害する作用があり
「食後の血糖値が気になる方へ」などと表記して販売されている。
〇⑵ SGLT2阻害薬は、尿細管での糖再吸収を抑制する。
SGLT2は、腎臓の近位尿細管に存在する輸送体で、
原尿から血糖(グルコース)を再吸収するはたらきがある。
SGLT2阻害薬によって、SGLT2のはたらきを阻害すると
血糖(グルコース)が再吸収されず、尿として排泄されていくので
結果として血糖値を下げることができる。
〇⑶ ビグアナイド薬は、肝臓での糖新生を抑制する。
ビグアナイド薬は肝臓での糖新生を抑制するはたらきを持つ。
「糖を新しく生み出す」ことが抑制されるので、
結果的に空腹時の血糖上昇を防ぐことができる。
また、末梢組織でのインスリン感受性も高める作用もある。
⑷ GLP-1受容体作動薬は、インクレチン分解を抑制する。
GLP-1は、インクレチンという消化管ホルモンのひとつで、
膵臓のβ細胞からのインスリン分泌を促進し、血糖値を下げるはたらきがある。
そのインクレチンは、DPP-4によって即座に分解されるため長時間インスリン分泌を刺激することはできない。
DPP–4によって分解されず、かつ、GLP–1と同じ作用を示すように開発された薬が
GLP-1受容体作動薬である。
なお選択肢の「DPP–4のはたらきを阻害し、インクレチンの分解を抑制する」のは
DPP–4阻害薬である。
〇⑸ スルホニル尿素(SU)薬は、インスリン分泌を促進する。
SU薬は、膵臓のβ細胞を直接刺激することで、半ば強制的にインスリン分泌を促進する。
他の経口血糖降下薬と異なり血糖値の高さに依存せず強制的にインスリン分泌が生じるので
低血糖の副作用に注意が必要である。
詳細は下記の動画を参照のこと。
文責:アヒル
😫 解説を読むのに疲れたら・・・
気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?
無料で試してみてね(期間中に解約で0円)
※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照
(PR)国試本番のためにマークシート専用の鉛筆は買った?