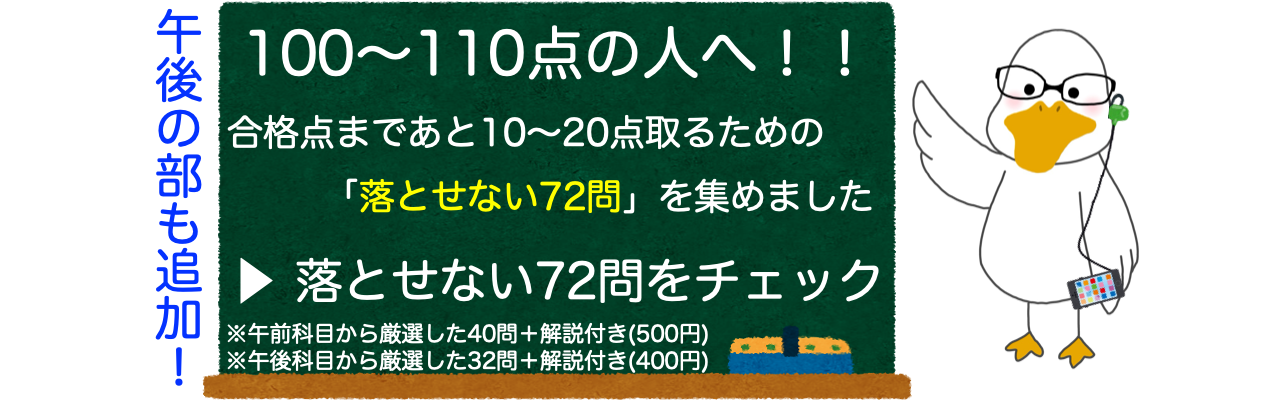問題文で鍵となるポイントは、下記の3点である。
実際に問題を解くときは該当部に下線を引けるなどしてほしい。
・ここ1か月ほど、ほとんど食事を摂れていなかった。
・患者が入院し、入院初日からエネルギー1,500kcal/日、アミノ酸45g、脂肪20gの静脈栄養が開始
・投与2日後、意識障害に陥り、K病院に転院した。
これら3点から、この患者は
長期間の飢餓状態(高度栄養不良)に高エネルギー(特に多量の糖)を補給することで生じる、
リフィーディング症候群による意識障害を起こしていると考えられる。
37-117に似た問題が出題されている。
よって、この問題は言い換えると、
「リフィーディング症候群のときの血液検査値の特徴は?」というものになる。
これを踏まえて選択肢を見ていく。
⑴ カリウム値の〔 低下 〕
⑵ マグネシウム値の〔 低下 〕
〇⑷ リン値の低下
リフィーディング症候群では、血清中のリン・カリウム・マグネシウムの3種類が全て低下する。
このまま丸暗記しても良いほど頻出項目であるが、リンだけはイメージしやすいので覚えておきたい。
〜リンに関して〜
長期の絶食が続くと細胞内はエネルギー源が枯渇する。
その状態で糖が供給されると、細胞は糖を取り込みエネルギーを産生しようとする。
このときのエネルギーとは、当然、ATPのことなので
細胞内ではAMP(アデノシン一リン酸)やADP(アデノシン二リン酸)に
リン酸をもう1〜2つ結合させて、ATPを合成する。
結合させるためのリン酸は血中から細胞に取り込んで利用することになるので
結果的に血中のリン(正確にはリン酸)の濃度は低下する。
〜カリウムやマグネシウムに関して〜
前述の「細胞は糖を取り込みエネルギーを産生しようとする。」とき、
糖の取り込みにはインスリンが関与する。
そしてインスリンによって糖が細胞内に取り込まれるとき
一緒にカリウムやマグネシウムも細胞内に移行する。
そのため、
糖が細胞内にたくさん取り込まれるとき→カリウムも細胞内にたくさん取り込まれることになり
血中カリウムや血中マグネシウムは低下する。
⑶ ビタミンB1値の〔 低下 〕
大量に供給された糖の代謝を活発に行うため、「糖代謝に必要なビタミンB1の要求量は増える」
つまり、ビタミンB1をたくさん消費することになるため血中のビタミンB1値は低下する。
※基礎栄養で頻出の「糖質をたくさん摂取したらビタミンB1の要求量が増加する」が分かっていれば解ける選択肢である。
⑸ インスリン値の〔 上昇 〕
大量に供給された糖により、一過性とはいえ血糖値は上がっている。
それに対応するため、インスリン分泌は増加する。
よって血中インスリン濃度は上昇する。
文責:アヒル
😫 解説を読むのに疲れたら・・・
気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?
無料で試してみてね(期間中に解約で0円)
※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照
(PR)国試本番のためにマークシート専用の鉛筆は買った?