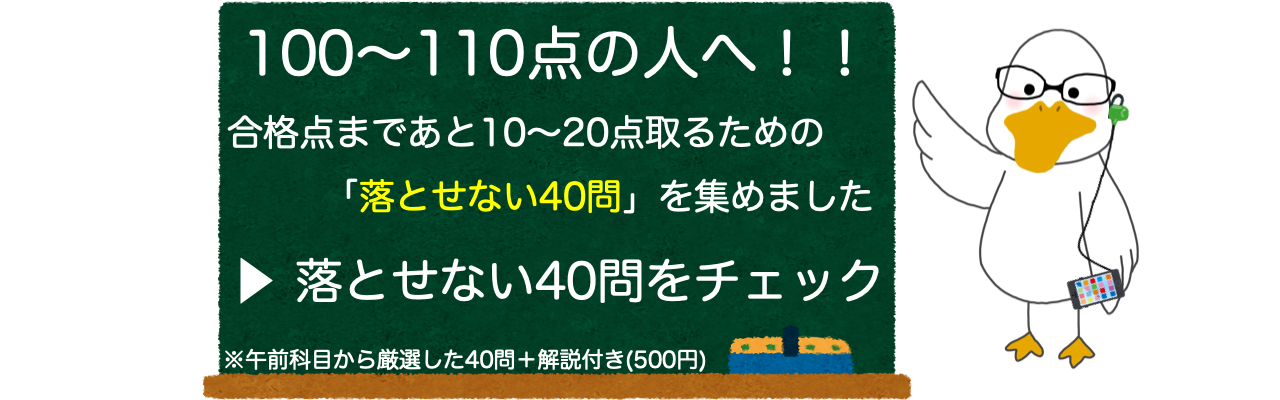日本食品標準成分表における各栄養素成分の分析方法がもとになった問題である。
37-50に同様の問題が出題されており、
組み合わせの左右をそれぞれしっかり覚えていれば対応できた問題である。
⑴ たんぱく質 〔 ケルダール法 〕
たんぱく質を測定する方法はケルダール法である。
基礎栄養の問題37-68(3)にもケルダールが登場している。
ケルダールはたんぱく質の窒素定量法を開発した人で、その実験方法にケルダールの名前がそのままついている。
このケルダール法を一部改良したものが日本食品標準成分表でのたんぱく質の定量に活用されている。
選択肢のカールフィッシャー法は、食品に含まれる水を測定する方法である。
※ケルダール法もカールフィッシャー法も37-50に出題されているので過去問で十分対応できる。
⑵ 脂質 〔 ジエチルエーテルによるソックスレー抽出法 〕
脂質の定量はジエチルエーテルを用いたソックスレー抽出法が用いられる。
⑶ 炭水化物 〔 差引き法 〕
炭水化物の分析方法の一つとして、差引法がある。
差引法は、食品100gから
水分、たんぱく質、脂質、食物繊維、有機酸
アルコール、灰分、その他(ポリフェノールやカフェインなど)を
すべて差し引いた残りを炭水化物量とみなす方法である。
〇⑷ 食物繊維 プロスキー法
正しい。プロスキー法は食物繊維を測定するための方法である。
⑸ ナトリウム 〔 原子吸光光度法 〕
ナトリウムやカルシウムなどの無機元素の分析には原子吸光光度法が用いられる。
文責:アヒル
😫 解説を読むのに疲れたら・・・
気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?
無料で試してみてね(期間中に解約で0円)
※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照
(PR)グルタミン酸から合成される「γ-アミノ酪酸(GABA)」→交感神経の抑制&副交感神経の亢進→リラックス