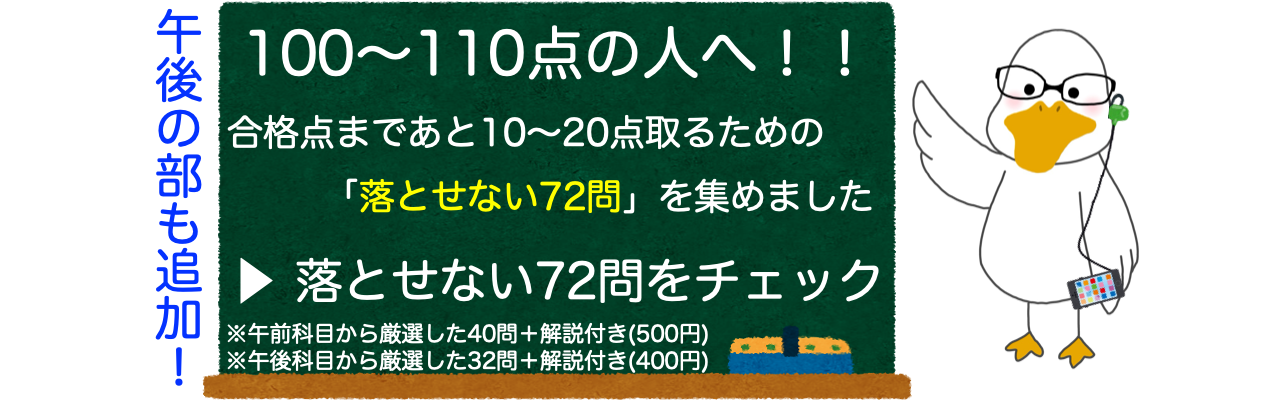⑴ ヒトのヘモグロビンは、〔 4本のグロビンからなる四量体である 〕。
ヒトのヘモグロビンは4本のグロビン鎖(α鎖とβ鎖がそれぞれ2個ずつ)からなる四量体 である、
⑵ ヘモグロビンと酸素の親和性は、ヘモグロビンと一酸化炭素の親和性よりも〔 低い 〕。
ヘモグロビンは酸素より一酸化炭素の方が数百倍レベルで強力に結合する。
そのため一酸化炭素中毒になった場合、高気圧の酸素を吸引させるなどをしてとにかく酸素を供給しなければならない。
〇⑶ 還元ヘモグロビン濃度が上昇すると、チアノーゼが出現する。
正しい。還元ヘモグロビンは酸素と結合していないヘモグロビンのことで、
還元ヘモグロビンが一定量を超えると、皮膚や唇が青紫色になるチアノーゼが出現する。
⑷ エリスロポエチンは、〔 赤血球の成熟 〕を促す。
エリスロポエチン(EPO)は赤血球の産生を促進するホルモンで、腎臓から分泌される。
腎不全などでエリスロポエチンが分泌されなくなると、赤血球が産生されなくなるので腎性貧血となる。
⑸ プラスミンは、〔 線溶系の酵素 〕である。
プラスミンはフィブリン(血栓)を分解する、線溶系の酵素であり、凝固因子ではない。
凝固因子は血液を固める役割 (例:フィブリノーゲン, フィブリン, プロトロンビン etc…)
プラスミンは逆に血栓を溶かす(線溶系)。
文責:アヒル
😫 解説を読むのに疲れたら・・・
気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?
無料で試してみてね(期間中に解約で0円)
※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照