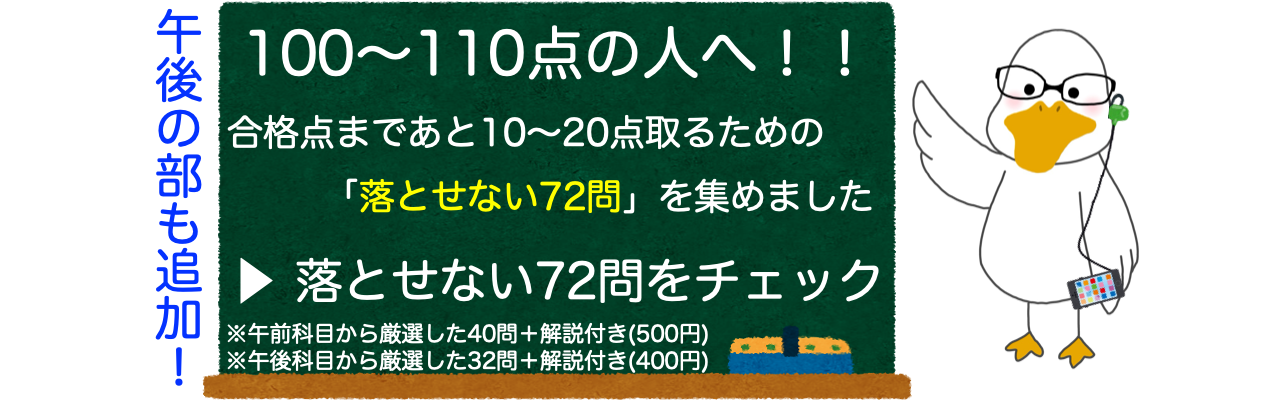⑴ 末梢静脈栄養では、〔 1,200kcal/日 〕の投与ができる。
末梢静脈栄養では、濃い(高浸透圧の)輸液を投与できないため比較的、薄い輸液を投与することになる。
その薄い輸液を2000kcalや2500kcal分も投与すると
大量の輸液を入れることになり、心臓などの循環器に負担がかかる。
そのため末梢静脈栄養では、〜1200kcal/日程度までしか投与できない。
※ちなみに、36-115, 34-114において、
「(誤)末梢静脈栄養では、2,000kcal/日の投与ができる。」という選択肢が出題されている。
この選択肢で「2,000kcalは多すぎる」と理解できていれば今回の2,500kcalが多すぎることも想像できた。
⑵ 末梢静脈栄養では、浸透圧比(血漿浸透圧との比)を〔 3以下 〕とする。
末梢静脈栄養では、浸透圧比を1〜3程度とする。浸透圧比5は高すぎる。
末梢静脈に、濃い(浸透圧の高い)輸液を投与すると炎症を起こしたりする可能性があり、
浸透圧比を1〜3程度(血液の浸透圧の1倍〜3倍程度)にするのが望ましい。
※ちなみにこの問題も36-115に「(正)末梢静脈栄養では、浸透圧比を3以下とする」
という正文の選択肢が登場している。
⑶ 脂肪は、〔 0.1g/kg/時以下 〕の速度で投与する。
脂肪は脂肪乳剤として投与するが、一度に大量に投与すると
血管が詰まるなどの症状(血栓症や脂質異常症など)を示すため
それらを回避するために0.1g/kg/時間以下で投与する。
つまり0.1g/kg/時間が上限で、それ以上は不適となる。
※ちなみに、36-115, 34-114において、
「(誤)末梢静脈栄養では、脂肪は1.0g/kg/時間以下で投与する。」という選択肢が出題されている。
この問題の選択肢も過去問周回で「1.0gは多すぎる。0.1g程度」と覚えていれば対応できた。
〇⑷ 中心静脈栄養では、糖質濃度20%の維持液の使用が可能である。
正しい。中心静脈栄養では、糖質濃度15~35%程度の輸液を使用することができる。
一方で、末梢静脈栄養では、糖質濃度7.5〜12.5%程度までしか使用できない。
どちらかを覚えて、もう片方は2倍くらい(or 半分くらい)で覚えておけば
国試の問題は対応できる。
※34-114に出題されている。以下同じ
⑸ 中心静脈栄養は、経腸栄養に比べてバクテリアルトランスロケーションを〔 起こしやすい。 〕
経静脈栄養などで腸管を使用しない状況が長期間続くと、
腸管表面の細胞が萎縮しボロボロになり、腸内細菌や細菌が生み出す毒素が
腸管から体内(血管内)へと移行してしまう。
これをバクテリアルトランスロケーションという。
上記の通り、バクテリアルトランスロケーションのきっかけは
経静脈栄養などで腸管を使用しない状況が長期間続くことなので
中心静脈栄養はバクテリアルトランスロケーションを起こしやすい。
文責:アヒル
😫 解説を読むのに疲れたら・・・
気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?
無料で試してみてね(期間中に解約で0円)
※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照
(PR)国試本番のためにマークシート専用の鉛筆は買った?